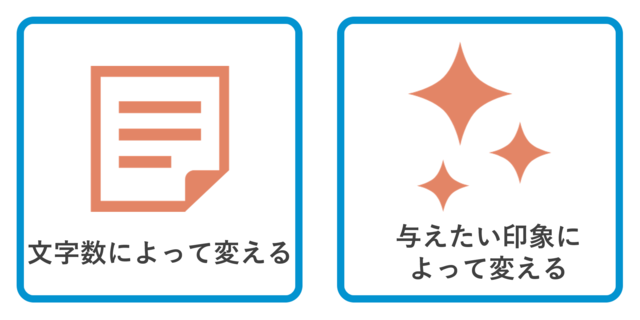履歴書
履歴書はですます・である調どちらを使う?|与える印象の違いをご紹介
- 120352 views
目次
履歴書はですます調で書くべきなのか
履歴書を書く際には、内容だけではなく語調にも注意が必要です。「ですます調」か「である調」のどちらにすべきか悩んでしまう人は多いでしょう。同じ内容で書いていたとしても、語調の違いによって与える印象は異なり、評価にも影響することが多いです。
履歴書は文章からその人の印象を読み取るため、どのような言葉を使うのかは非常に重要なポイントです。書き方ひとつで合否に影響することもあるため、語調をどうすべきかをしっかり考えておかなければなりません。履歴書で使用する語調を選ぶためには、それぞれの特徴を把握することが大切です。ですます調とである調、それぞれの特徴を把握して、どちらが履歴書にふさわしいかを考えてみましょう。
履歴書はですます・である調どちらがいいのか
履歴書はですます調かである調、どちらで書くかで与える印象が大きく異なります。印象が違えば当然評価も異なるため、上手に使い分けなければなりません。それぞれの特徴を把握して、シーンに合わせて上手に使うことが、書類選考を攻略する秘訣です。また、そもそも履歴書では、どちらがふさわしいのかを考えることも大切です。語調による違いを把握して、ですます調とである調、どちらで書けばいいのかを考えましょう。
ですます調は丁寧な印象
ですます調は丁寧な印象を与えることができ、柔らかい人間性をアピールしやすいです。履歴書では記入する内容はもちろん、マナーを持った対応が求められますので、丁寧さをアピールするのは大切なことです。いかに素晴らしい内容でアピールできていても、マナーをきちんと守れていなければ、マイナスの印象を与えてしまうので注意しなければなりません。
もちろん、ですます調を使ったからといって、必ずしも丁寧な印象を与えられるとは限らないため、言葉遣いには十分注意が必要です。また、ですます調は丁寧な印象を与えられる分、自己主張が弱い印象を与えてしまうこともあります。自信を持って内容を記載しましょう。
である調は意思が強い印象
である調は、ですます調とは違って意思が強い印象を与えられます。はっきりとしたアピールができるため、より印象深く自分をアピールする際に用いられることが多いです。である調の場合は、気持ちが伝わりやすく、アピール力が高い分、言葉が強く見えやすいので注意しなければなりません。
強すぎる言葉は、場合によっては失礼になることもあり、マイナスの印象を与える危険性があることは理解しておきましょう。また、アピール内容によっては、自意識が強く、頑固な印象を与えてしまうこともあります。である調は全体的にすっきりとしたアピールがしやすい反面、言葉の選び方によっては、誤解されやすいことは頭に入れておきましょう。
39点以下は危険水域!
企業にメールする前にマナー力を診断してください
「面倒くさいな…」と思いがちな就活マナーですが、いざというときにできていないと不合格の原因になることも。
不安な人は「マナー力診断」を活用しましょう。39点以下の人は本番前に改善が必須です。
今すぐ診断して、自信を持って就活に臨んでください。
混在させないことが大切
履歴書では、ですます調とである調のどちらを使用しても問題はありませんが、これらを混在させてしまうのはNGです。ですます調で書き始めれば、ですます調で統一して最後まで書き上げなければなりません。途中で語調を変えてしまうと印象が悪くなるので注意しましょう。
語調が変わると読みづらくなり、アピール力は下がります。加えて一貫性がない印象を与えてしまい、場合によっては信頼できないと判断されることもあるので注意しなければなりません。同じ内容でも語調によって与える印象は違うため、途中で変えてしまうと、伝わる人間性も違ってしまいます。人間性が把握できず、どんな人柄なのかが理解できなくなるため、混在させないよう注意しましょう。
項目ごとに変えるのはOK
一度書き始めれば語調を混在させるのはNGですが、項目ごとに変えるのであれば問題はありません。たとえば志望動機はですます調、自己PRはである調など、項目ごとに完結していれば、語調を変えてもマイナスの印象は与えずに済みます。
項目ごとに変えずに、履歴書すべてで語調を統一させても問題はありませんが、項目ごとに変えることで、より印象的にアピールがしやすくなる可能性もあります。自己PRは自分を売り込むための文章なので、である調ではっきりと言い切ってしまうのもアピール方法のひとつです。
対して志望動機は、採用担当者に向けての文章になるため、丁寧な印象を与えたほうが印象がいいでしょう。わざわざ使い分けをしなくてもいいですが、変えていいことは覚えておくと便利です。
履歴書作成マニュアルについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
履歴書での語調の使い分け方
履歴書ではですます調とである調、どちらを使用しても問題はありません。しかし、どちらでも使用できるとなれば、どちらを使ったほうがいいのかと悩む人は多いでしょう。語調はどちらか一方で統一させても、項目ごとに使い分けてもいいですが、どちらの場合でも、使い分けることが大切です。
文字数によって変える
語調を使い分ける際は、全体の文字数によって変えるのがおすすめです。全体的に量が多くなる場合はである調、少ない場合はですます調と使い分けてみましょう。同じ文章でも、語調が違うだけで文字数は異なります。たとえば「私の長所は優しいことです」という文章でも、である調に変えれば「私の長所は優しいことだ」となり、1文字減らすことができます。
1文単位で見ればわずかな差ですが、これが積み重なれば大きな違いになるため、語調で量を調整するのはおすすめです。また、これはエントリーシートを記入する際にもおすすめの方法であり、エントリーシートの場合は履歴書より明確に文字数が指定されていることも多いです。全体のバランスを考える際には、語調の変化も試してみましょう。
与えたい印象によって変える
語調によって与えられる印象は異なるため、与えたい印象に合わせて使い分けるのもおすすめです。語調を選ぶ際には、どんな印象を与えたいのか、イメージを明確にしておくことが大切です。基本的には柔らかい印象を与えたいならですます調、活発な印象を与えたいならである調を選びましょう。
自分のキャラクターに合わせた使い分けも大切ですが、志望業界や企業に合わせて使い分けることも大切です。業界や企業によって求める人材像は違い、志望先に求められる特徴に応じて、語調を変えるのもいいでしょう。語調の変化によって、特定の人柄を強くアピールすることもできれば、弱い部分を補うこともできます。与えたい印象をしっかりイメージして、適切な方を選びましょう。
39点以下は危険!
選考前にあなたの就活力を診断してください
就活では気をつけるべきことが多いです。いざという時に「その対策はしていなかった…」と後悔したくないですよね。
後悔せずに就活を終えたい人は、今すぐ「就活力診断」で診断しましょう。たった30秒であなたの弱点を判定し、これからするべき就活対策がわかるようになります。
無料で使えるので今すぐ診断し、就活で後悔しないようになりましょう!
ですます調は敬語表現が自然に使いやすい
履歴書ではですます調とである調、どちらを使用しても構いませんが、敬語表現を使いやすいのはですます調です。ですます調は丁寧な印象を与えやすいだけではなく、文章自体の性質から、敬語表現にスムーズに繋げられます。
対してである調の場合、強く言い切る形になるため、敬語表現に繋げることが難しく、場合によってはぶっきらぼうな印象を与えてしまいます。もちろん、内容次第で印象は変わり、上手に使えばである調で高評価を獲得することも可能です。
シーンに合わせて使い分けることが大切であり、それぞれの特徴を正しく理解しておく必要があります。語調によって評価は違ってきますので、上手に使い分けて、アピール力の高い履歴書を作成しましょう。